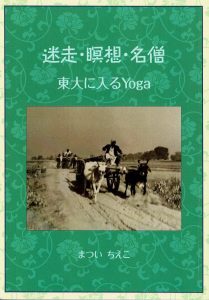台湾の友人、王さんから私のフェイス・ブックを見て、瞑想合宿最終日に熊肉を食べたこと、お酒を飲んだことに対して質問が来た。坂本がいつも提唱している非暴力・不殺生と矛盾しないかとの質問だった。
ちょうど良い機会なので食べ物の非暴力について私の考え方をまとめてみたいと思った。
人間の生き方は聖の立場と俗の立場があると思います。聖なる生き方は出家の生き方です。私たちがイメージする日本の宗教家や普通のお坊さんは出家であって出家ではないと思います。出家の顔をした俗人です。出家といわれる人が王様のような暮らしをして、企業経営者のような金儲けをしています。私はジャイナ教の出家僧に出会ったとき初めて本物の出家のことが解りました。彼らは本当に無所有を実践し、本物の非暴力を実践していました。
私達の生き方は俗の生き方です。結婚し家族がいて家族を養う為に仕事をしなくてはなりません。様々なしがらみに縛られているので完全なる聖の生き方は出来ません。世俗的生活では完全なる無所有も完全なる非暴力も実践出来ません。企業経営者であればライバルとの競争に勝ち抜かなくては企業を存続出来ません。競争に負ければ業績不振となり従業員に給料も出せなくなり倒産もありえます。倒産した会社の社員は失業し苦しむこととなります。スポーツ選手も勝ち抜かなければ栄光は得られません。俗世界は一にぎりの勝者と多くの敗者があって、良く考えれば競争と暴力うずまく社会といえます。
聖なる出家の世界には他との競争がありません。闘いは自分自身との闘いだけです。自分をいかに清らかにするかという実践が自分自身との闘いだから、他に対する完全なる非暴力が実践できるのです。仏陀もジナも出家しない世俗的生き方では解脱出来ないとして出家を勧めました。
出家の教えである完全なる非暴力は世俗的生活では困難です。そこで厳しい出家の戒律と緩やかな世俗の戒律が出来たのです。世俗の人間に対して出家の戒律をあてはめても無理があります。
私は世俗の立場の生活者なので、私に聖人に対するような要求をしても私には実践できません。沖ヨガの沖正弘先生は生前、弟子たちに「お前たちには俺のような聖なる生き方は無理だから、半俗半聖で行けよ」とよく言われていました。私の生き方は俗なる生き方の中に、聖なる生き方を取り入れて、バランスよく人間的に生きるというのが今生のテーマです。
私は俗人の立場で聖なる生き方を実践し提唱しているのであって、私は出家した聖者ではありません。ヨガや瞑想を実生活で生かすにはどうしたらいいかを実践し、俗の立場で提唱している単なる教師です。つまり私は「俗が聖をやっている」のです。世に聖人、出家といわれている人の多くが全くの俗人で「聖が俗をやっている」のがほとんどです。どちらがより善い生き方かと考えて私は「俗が聖を行じる」方を選択しているのです。
以下は食べ物に対する宗教的な非暴力の考え方を半俗半聖の立場で考察したものです。人間が食べ物を食べるとき、その食べ物は何らかの生命を殺しているか傷つけていることになります。植物も生き物です。完全なる食の非暴力は全く食べないことです。人間は生きている以上、何らかの食べ物を食べなくてはなりません。人間に近い哺乳動物を食べるのはなるべく避けて、穀物や野菜中心の菜食にすべきだという見解は非暴力の実践として説得力を持っています。そういう観点からすればバナナや果物、木の実だけを食べるのが一番善いことになります。
私は食べ物に善悪は無いと考えます。適応性拡大の為に食べ物の善い悪いの判断を止めることだと思います。食べ物を区別すると自由を失います。外国に行くと文化や食生活が違うので、時には食べた事の無いようなものを食べなければならないときがあります。何でも食べることが出来れば何処へでも行けます。子供のころ蛇が怖かったのですが、マムシを食べたら蛇に対する恐怖が無くなりました。それからは蛇の生息する山にも行くことが出来るようになり、蛇と出遭ったときには、私はお腹が空いていれば蛇を食糧とすることが出来るので蛇が私を見て逃げていきます。以前は私が蛇から逃げていました。
非暴力の観点から日本人に魚を殺してはいけない、魚を食べてはいけないとは云えないでしょう。魚を食べることは日本の文化であり伝統だからです。海に囲まれた日本は新鮮でおいしい魚が身近で容易にとれます。我々の先祖は米と野菜と魚を食べてきました。牛や豚など家畜を飼育して食べる習慣はありませんでした。明治以降西欧文化の影響を受けて肉食が始まったのです。
印度は暑い気候の国です。海から遠い印度の内陸では新鮮な魚は入手困難です。家畜の肉も暑さで食べる前に腐敗が進んでしまいます。健康の面からも魚や肉を食べる文化は育ちません。印度で魚や肉を食べてはいけないというのは道理に合っています。印度は暑い国なので香辛料を使った辛い料理、砂糖を沢山摂取しています。日本人が同じような食生活をしたら健康は保てないでしょう。同じように印度では気候が暑すぎて発酵食品の文化は育ちませんでした。発酵食品文化は日本で発達しました。日本は発酵食品の国といっても過言でありま
せん。台湾の食事は日本に比べて味付けが薄く、塩気が少ないのも気候の相違によるのです。台湾の人が日本人に比べて身体が柔軟なのは気候によるのです。日本人が風呂好き温泉好きなのは体の塩抜きの為に必要なのかもしれません。
草原の国の人々の肉食文化、エスキモーの人々のアザラシなど海獣の内臓まで食べる文化、それを暴力と責めることは出来ません。その土地に生きる人にとって必要なことであり、カルマなのです。ジャイナ教では印度に生まれて完全なる食の非暴力を実践しないと解脱は得られないとしています。ならば、日本人が解脱を願うなら来世で印度に生まれることを願うしかありません。
只見では江戸時代まで牛や豚は食べませんでした。古代から日本には鹿やイノシシ、カモシカ、熊などの野生動物を狩猟する狩人の食文化がありました。熊狩りする特別な狩人をマタギといいます。只見にもマタギの伝統がありました。今ではほとんどいなくなってしまったマタギの一人が、友人の長谷部義一さんです。
瞑想合宿の終わる前日、厳しかった修行の最終日の夜は、俗界に帰る準備です。今日まで7日間禁酒、ヨガ式自然食だったので、陰陽刺激の総仕上げとして、緊張の反対、緩めて放下する刺激の一つとして夕食時にお酒を出す予定でいました。マタギの義一さんとは一年近く会っていませんでした。丁度その日の午後、義一さんは坂本さんに会いたくなったと番所にやってきて、自ら仕留めた貴重な熊肉を差し入れてくれました。私から熊肉を食べたくて求めたのでなく、向こうからやってきたのです。チベットの聖者ミラレパがイラクサだけ食べて体が緑色になり生きているのが不思議なくらい骨と皮だけになって洞窟で瞑想修行していた時、猟師から獣の肉の喜捨を受けました。そのときミラレパは人間らしい食べ物だと言って喜んで獣の肉を食べたと言う伝説もあります。
食べ物はまずいより美味しいほうが良いと私は考えています。食べ物は舌で食べるのではなく、体を養う為に食べるのだとの主張は一見真実のようですが、半分真実で半分は嘘です。確かに美味しいものだけ追求し美食に偏ったら体を壊します。味はどうでもよく体に良いものを食べるというのも人間的でなく偏りの一種です。欲望をコントロールする意味で食をコントロールするのは良いことです。本当の出家は托鉢によってしか食べられません。食べ物を選択出来ません。現代仏教の托鉢は形骸化してミャンマーやタイの坊さんたちは毎日、在家から食べきれないほど沢山の美味しい食べ物の喜捨を受けて糖尿病や高血圧、肥満で苦労しています。皮肉なことに苦しくても沢山食べることが修行のようになっています。断食は食欲のコントロールと美食による弊害の体調回復にとても良いので、短期の絶食や断食を日常生活に取り入れることを勧めます。
料理人にとってはより美味しく食べ物を作ることが愛です。また、世俗の人が美味しいものを食べて味覚を満足させ人間的喜びを得ることは悪いことではありません。美味しさを追求しなかったらテレビの料理番組は成り立ちません。
美味しい料理はその国の文化です。私たちは俗人なのですから、出家の立場の非暴力・不殺生は困難です。現実というものを大事にしないと混乱し行き詰まってしまいます。完璧に非暴力・不殺生を実践したかったらジャイナ教の出家僧になるしかありません。
栄養補助剤・サプリメントはそのすべてが体の中で吸収されて栄養になるわけではありません。食べ物も同じです。身体が食べた物の養分を不要と判断すれば、それを排泄してしまいます。また、食べた物によって必要な栄養が得られない時には身体は栄養を合成する能力を備えています。その良い例として、50年ほど前まで、チベットの僧侶は麦粉がしを練ったツアンパとバター茶だけしか食べていませんでした。それでも元気に生きていけたのです。身体を効率よく機能させるために微量元素も必要とされているわけですから、サプリメントに頼るばかりでなく、いろいろな食べ物を食べるのが良いとされています。飲用に適した温泉水を少量飲用すれば免疫力やアレルギーの予防になると思います。
食品添加物の問題は深刻です。これからの時代は自分の食べる物を自分でつくるのが最高の食の贅沢になるでしょう。ヨガの実践と食の自給自足が時代のテーマになりつつあります。ジャイナ教哲学では農業が出来ないので、私達は現実的、実際的な江戸後期の哲人・二宮尊徳の教えをあわせ学ばなければならないと思います。
不殺生は殺すなという意味ですが、積極的には生かしなさい、活用しなさいということです。見捨てられて死んだものを活用することが本当の非暴力だと私は考えます。人間や生き物だけでなく、食べ物を含めてあらゆる物を粗末にしないということも非暴力です。
私たちは他の命をいただいて生きていけるのだから、その御恩に報いる生き方、恩返しの生き方をしなければならないというのが沖正弘先生の食養の言葉です。感謝、懺悔、下座、奉仕、愛行が食べ物をいただく姿勢です。それが正しい生き方であると信じています。
<著:坂本知忠>
(協会メールマガジン2013/8/23からの転載です)